親にウソをついて弁当を忘れて唐揚げ弁当を注文!
目次
1.年に数回ある「お弁当」は誰がつくる?
ほとんどの公立小学校、公立中学校には給食があります。
※ 地域によっては「小学校だけ」「小学校と中学校の両方」とも給食がない学校もあります。
ただ、年に数回は行事の関係などで家から「お弁当」をもっていく日があると思います。
そんな日は、保護者の方が朝早くに起きてお弁当を作ってくれるでしょう。
もちろん、自分でお弁当を作って持ってくる子供もいます。
余談ですが、中学校時代に自分で作った「チャーハン弁当」を持ってくる友人がいました。
弁当箱いっぱいに「チャーハン」が詰まっている、おかずなしの弁当です。
そのチャーハンがとてもおいしそうに見えた私は、自分の「おかず」と「チャーハン」の交換を持ちかけました。
そのチャーハンを一口食べた私は次のように思います。
「なんて、おいしいチャーハンだ!」
「うちのお母さんよりおいしい!」
「お店の味みたいだ!」
現在も「私が作るチャーハン」は、その友達に教えてもらったレシピを使用しています。
2.先生たちは「お弁当」をどうしてる?
給食のない日、先生たちはどうしているのでしょうか?
自分で作った「お弁当」を持ってくる先生もいます。
朝、近くのコンビニで弁当を買ってくる先生もいます。
前日に、用務員さんが希望者の弁当を注文してくれる学校もあります。
当日、先生が弁当を忘れていたとしても、2時間目位までであれば「追加注文」できたりもします。
注文した弁当は「用務員さん」や「担当の先生」が取りに行ったり、配達してもらったりします。
3.荒れた学校には「ご機嫌を伺う」ルールばかり!
ある市のA中学校は「荒れ」ていると評判の学校でした。
私は「教育委員会」と「校長」「前生徒指導主事」のご指名で、A中学校の生徒指導主事として勤務することになりました。
その学校の「ルール(?)」には驚くべき事がたくさんありました。
この「ルール(?)」は、学校が荒れたことによって、もしくは、子供たちや保護者の「ご機嫌を取る為」にできた「ルール(?)」でしょう。
私が驚いた「ルール(?)」には次のようなものがありました。
・お弁当を忘れたときのルール。
・傘を忘れてしまった時のルール。
・上履きを忘れてしまった時のルール。
・窓を割ってしまった時のルール。
・宿題を忘れて(やらなかった)時のルール。など
4.弁当を忘れないように3日前から呼びかけ!
お弁当を持ってくる日の3日前。
私は帰りの会で次のような声かけをします。
「明明後日はお弁当だからね~。」
「家の人にちゃんと言うんだよ!」
「もちろん、自分で作ってくるのも良いかもね!」
「お弁当を作る人の大変さが分かるんじゃない!」
「先生の教え子に料理が趣味で常にお弁当を自分で作ってくる子がいたよ。」
「自分で作る、作らないは置いておいて、忘れないでよ!」
「絶対に忘れないでよ!」
すると、ノリの良い子がツッコミを入れます。
「先生!」
「それは、逆張りって事ですよね!」
「忘れるなを何度も言うってことは、忘れろって事でしょ!笑」
「押すな、押すなと一緒なんでしょ!笑」
彼と私は3日間、同じやりとりを繰り返しました。笑
5.弁当を忘れたらスグに家に電話!
前日の帰りの会では、もう少し細かい話も伝えます。
「明日はお弁当を絶対に忘れちゃダメだよ!」
「忘れたら、すぐに家に電話して持ってきてもらってよ!」
「学校では買うことが出来ないからね!」
すると、1人の子供から質問の手が上がります。
「先生~。」
「万が一、忘れちゃって、家に誰もいなかったらどうするの?」
私が質問に答えます。
「まずは会社に電話するでしょ。」
「それでもダメなら・・・。」
6.連絡がつかなかったら・・・・
「それでもダメなら・・・。」
「その時は先生が買って来るよ!」
子供たちからは次のような声が聞こえます。
「先生って優しいね~!」
「○○の弁当を買ってきてくれるの?」
「そっちのが良いな~。」
「明日、忘れて来ようかな~。笑」
すかさず、私は「優しくない」理由を伝えます。
「先生が買ってくるのは『食パン』と『ジャム』だよ!」
「もしくは『梅おにぎり』5個!」
「バナナ3本とかの場合もあるよ~。」
7.「お弁当を忘れた子0人」に驚く主任
翌日の朝、子供たちにお弁当を忘れていないかを確認します。
「お弁当を忘れた子はいない?」
3日前からの声かけと脅し(?)がきいたのか、お弁当を忘れて来た子供は一人もいませんでした。
授業の前に私が職員室に戻ると主任が声をかけてきます。
「お弁当を忘れた子は何人?」
「何個、注文すればいい?」
主任の質問には違和感があります。
ただ、1時間目の授業に向かうために、急いでいた私は違和感を無視して答えます。
「0人です!」
すると学年主任が驚きと困惑の表情で聞き返して来ます。
「えっ本当ですか?」
「誰も注文しないんですか?」
8.担任の机の上にお弁当が5個!?
4時間目が空き時間だった私は職員室に戻ります。
書類の整理を始めて少し経つと「お弁当屋さん」が職員室に弁当を持ってきてくれました。
私は副担任が持っていたメモを元に「弁当を注文した先生」の机の上に、弁当を置いていきます。
「えっ?」
「B組の先生の机の上にお弁当が3個?」
「C組は2個だけど、D組は1個?」
「E組は5個?」
「F組は4個?」
私は副担任に「弁当の数」について聞きました。
「お弁当を忘れた子の分を注文しているんです。」
「B組は2人、C組は1人、D組は0人、E組は5人、F組は4人です。」
私の学年は6クラスで生徒数は約200人です。
その中で弁当を忘れた子が「12人」いたのです。
放課後に他の学年に確認をすると、2年生(6クラス)は「19人」、3年生(6クラス)は「24人」もの子供が弁当を忘れて(?)いた事が分かりました。(合計55人)
9.忘れた子は好きなお弁当を注文できる!
この学校の「弁当ルール(?)」はどうなっているのでしょう?
放課後、私はA中勤務歴5年のE組担任に聞いてみました。
「お弁当を忘れたからといって昼食を抜きにはできません。」
『そりゃ、そうですよね。』
「本校では、忘れた子供の弁当は注文するようにしています。」
「もちろん、代金は後から払ってもらいます。」
『まあ、それはアリだよね。』
「弁当を注文してあげるのは『いじめ防止』の意味もあります。」
『ん?』
『それは、ちょっと違うような・・・。』
「朝、弁当の確認をして忘れた子にはメニューのコピーを渡します。」
『ん?』
『もしかして?』
「子供はメニューから食べたいお弁当を決め、担任に伝えます。」
「担任は主任や担当に弁当の種類を伝え、注文してもらいます。」
私は弁当の注文数について確認します。
「1学期から3学期にかけて、注文数は増えるのではないですか?」
「1年から3年にかけても、注文数が増えるのではないですか?」
E組担任の回答は予想どおりのものでした。
10.「弁当ルール(?)」が出来た背景は?
荒れている学校の先生たちは、子供に対して「注意ができない」「指導ができない」「反論ができない」状態にあります。
ただ、先生たちは「できない」ということを認めたくないようで、「理想論」を盾に自分を守る傾向にあります。
実際、岩谷先生以外にも「弁当ルール(?)」の話を聞くと、次のように仰っていた先生もいます。
「子供たちの成長のためにバランスの良い食事が大切だと思います。」
『それなら、弁当を選ばせるのはおかしいのでは?』
「仕事をしている親が多いから、電話で持ってきてもらうのは申し訳ない。」
『親の為ではなく、親と電話で話すのが面倒なのでは?』
『何か文句を言われるのがイヤなのでは?』
実際、「弁当のルール(?)」ができた理由は「子供のことを思って」ではないように思います。
本音の所では次のような理由ではないでしょうか?
「お弁当を忘れた子を注意するのは面倒だ!」
「逆ギレされても困るし、自分が買いに行くのもイヤだ!」
「親に電話して、ムリなことを言われるのもいやだ!」
「それなら、教師と一緒に注文すればいいじゃん!」
「そうすれば、子供も満足するだろう!」
「親も感謝してくれるだろう!」
11.弁当についての極秘調査命令を受ける
私は「弁当ルール(?)」について、赴任したばかりの校長に伝えます。
すると「弁当ルール(?)」に驚いた校長は、私に「極秘調査」を命令しました。
その結果は次のようなものでした。
・弁当の「回数を重ねる」ごとに、注文する子供が「増え」ている。
・1年生→2年生→3年生の「順」に、注文する子供が「多く」なっている。
・注文を「2回以上」したことがある子供が「9割」を超えている。
・弁当を忘れている子の中には「いじめ被害者傾向」の子供は「0人」である。
※ どちらかというと「いじめ加害者傾向」の子供ばかりでした。
・最も人気のある弁当は「唐揚げ弁当」で、栄養のバランスは「悪い」ものだった。
また、弁当を「2回以上」注文している親には電話でアンケートを行いました。
すると、親御さんたちが子供たちから「次のように言われている」ことも分かりました。
「クラスのみんながお弁当をコンビニで買っている!」
「みんなと同じにしないとバカにされる!」
「自分でコンビニ弁当を買うから金をくれ!」
学校で「弁当を注文している」ことを知っている親は数人だったのです。
12.弁当事前事後マニュアル作成(笑)
バカバカしい話ですが、その年の夏休みに生徒指導部で「弁当事前事後マニュアル」を作成しました。
これにより、弁当を忘れる子供が激減します。
もちろん、弁当を忘れてしまった子に対して、次のように言うことはありません。
「忘れたお前が悪い!」
「お腹がすいても我慢しろ!」
「我慢できないなら、その辺に生えている草でも食ってろ!」
弁当を忘れてしまった子供に対しては「次回以降に忘れないように注意」をして、学校で弁当を用意したのです。
ただし、自分でメニューから選ぶ訳ではなく、次の2つから選んでもらうことにしました。
「幕の内弁当」or「ノリ弁当」
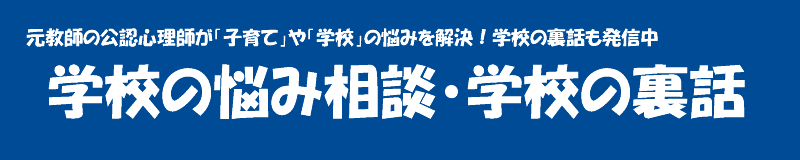



コメント