荒れている学校の「教師」は時間にルーズ
目次
1.教科担任には事前に声かけの具体例を!
私は各教科の先生たちに、事前に声のかけ方のお願いをしておきました。
「子供たちには2分前着席を伝えています。」
「入学したての子供たちは、2分前着席を守ろうとガンバっています。」
「子供たちが授業開始のチャイムのときに座っていたら、褒める声かけをお願いします。」
「この時期にガンバリを褒め、認めることで、子供たちの中で2分前着席が普通になります。」
「申し訳ありませんが、子供たちのガンバリを褒めてください!」
また、授業の終了時間について、国語、数学、社会、英語の先生にお願いをしました。
「授業は終了のチャイムと同時に終わりにして下さい。」
「次の授業が音楽や家庭科、技術、理科など特別教室の授業のときは注意して下さい。」
「1年A組は特別教室から最も遠い教室になります。」
「そのため、少しでも授業が延長すると、次の授業に間に合わなくなってしまうんです。」
逆に音楽や技術、家庭科、理科、体育、美術の先生には、遅刻のときの指導についてお伝えさせていただきました。
「遅刻をしたときは指導をして下さい。」
「先生方の考えに合わせて注意をお願いします。」
「ただ、次のような声かけだけは止めて下さい。」
『教室が遠いから、遅刻しても仕方ないよ!』
『別に授業に遅れても良いからね~。』
2.「遠いから仕方無い」はNGワード!
1年A組は様々な場所から、最も遠く離れています。
下駄箱からも最も遠く、職員室からも最も遠く、グランドや体育館にも最も遠く、音楽室や理科室にも最も遠い場所です。
しかし、私は子供たちに授業開始時間には着席しているように言います。
私の「開始時間」の考えについて、次のように思う方は少なくありません。
「遠いんだから間に合わなくても仕方ない!」
「子供たちがかわいそう!」
事前に「指導」をお願いした先生の中にも、同じように仰る先生もいました。
※ 荒れているA中に何年もいる先生たちは「遅刻は仕方ない」と言っていました。
それでも、私は音楽や美術、理科、体育、家庭科、技術の先生に「指導」をお願いしたのです。
3.授業開始時間にこだわる2つの理由
私が「授業開始」時間にこだわる理由は2つです。
1つ目は、「学級崩壊」クラスは「授業の開始時間を守れない」ということを知っているからです。
逆説的になりますが、「授業の開始時間を守るクラス」で「学級崩壊」しているクラスは見たことがありません。
2つ目は、学校のルールを「個々の教師の判断」で変えてしまうと、学校が「荒れる」と分かっているからです。
例えば、校則で「くるぶしソックス」禁止という項目があったとします。
『靴下なんて何だって良いじゃん!』
『何でくるぶしソックスっがダメなの?』
このように考える先生も少なくないでしょう。
(実際、私も同じように思っています。)
しかし、自分の判断で「ルールを破っている子供」を見て見ぬ振りをしてしまうと・・・。
子供たちは学校のルールを軽視するようになります。
→小学校の先生が中学校を荒れさせた
もし、そのルールが間違っていると思うのであれば、職員会議で戦えばいいのです。
実際、私は「くるぶしソックス」の校則廃止を職員会議で訴え続けました。
その結果、2年ほどかかりましたが、校則を変えることができたのです。
4.時間のルーズさを指摘!改善案を!
5月の職員会議。
私は生徒指導主事として、A中の1ヶ月間を見た感想を伝えます。
※ 本当はダメな所だらけなのですが、ダメ出しばかりでは「勤務の長い先生方」の反感を買うので、ポイントを1つに絞りました。
「4月から生徒たちを見てきて気になるポイントがあります。」
「それは、時間に対するルーズさです。」
「落ち着かない学年の子供たちのほとんどが時間を守る意識が希薄になります。」
「逆に考えると、時間を守る意識ができれば、学級や学年は落ち着いてきます。」
「注意したり、怒ったりしろとは言いません。」
「ただ、子供たちが時間に遅れたときは、声をかけて下さい。」
「声をかけたからと言ってスグに時間を守れるわけではありません。」
「しかし、声をかけなければ、悪くなる一方です。」
新しく赴任してきた校長が、私の発言に賛同してくれました。
「西川先生の仰る通りだと思います。」
「時間を守る意識が身につくように、声をかけていきましょう。」
5.教室が遠いから授業に遅刻しても仕方ない?
私の次は「学習指導部長」の矢野先生が提案をする番です。
矢野先生も4月からA中学校に赴任している先生です。
「偶然ですが学習指導部の提案は生徒指導部と同じです。」
「生徒たちに、授業開始時間を守らせたいと思います。」
「その為には、先生方も授業開始時間には教室(特別教室)にいるようにして下さい。」
「また、生徒たちが遅れてきた場合は声をかけて下さい。」
この提案に対して、3年部の主任である渡壁主任が意見をします。
「前の授業が伸びてしまったりした場合、授業に遅れるのは仕方ないと思いますよ!」
「また、教室と違って特別教室や体育館に行くには時間がかかります。」
「開始時間を守らせるのは大切ですが、ムリなことを強要するのはかわいそうですよ!」
渡壁主任の発言は「子供たち」のことを考えての発言なのでしょうか?
それとも、3年生が授業開始時間を守れないことの「保険」なのでしょうか?
※ 3年生の教室は全て旧校舎にあり、体育館や特別教室に最も近いのですが・・・。
6.「休み時間を5分延長して!」は却下された
私も子供たちに「ムリ」を強要するのは好きではありません。
そこで、この学校で最も体育館や特別教室に遠いクラスの担任である私は、次のような提案をします。
「ムリを強要するのは良くないというのに賛成です!」
「しかし、授業開始時間を守るのは大切だと思います。」
「私の1年A組は新校舎4階の最も奥にあります。」
「そのため、子供たちは移動教室に間に合うように常に時間を意識しています!」
「そこで、ムリを強要せず、開始時間を守れるようにする提案をさせて下さい!」
『全ての休み時間を5分延長して15分とする!』
もちろん、私の提案は却下されました。
「休み時間を延長すると混乱が生じる。」
「友だち同士のケンカやトラブルが増える。」
「他の学校の休み時間は10分だからA中だけ変えるのは・・・。」など
教頭や主幹教諭、学年主任たちの反対意見は、どれも非論理的なものでした・・・。
最終的には次のような決着となりました。
「休み時間は10分のママとする。」
「なるべく授業開始時間を守るように声をかける。」
7.教師個人の判断で「遅れて良い」は×
入学してから1ヶ月半の間、時間を意識して生活をしてきた1年A組の子供たちは、その後も時間を守り続けます。
もちろん、前の授業が延びて「授業に遅れる」場合も一言「すみません」と言えば教師側か怒ることはしません。
理由はどうあれ「遅れてすみません」の一言が生徒指導では大切になります。
ここで、自分の「優しさ」をアピールしたい教員は次のように言ったりします。
「ムリしなくて良いからね~。」
「遅れても仕方ないよね~。」
「授業の開始に間に合わなくて良いんだよ~。」
この言葉を聞いた生徒たちが、「感謝」の気持ちを持って、次からも時間を意識してくれれば良いのですが・・・。
このような声かけにより、学級や学年が崩壊していく事は珍しくないのが現実なのです。
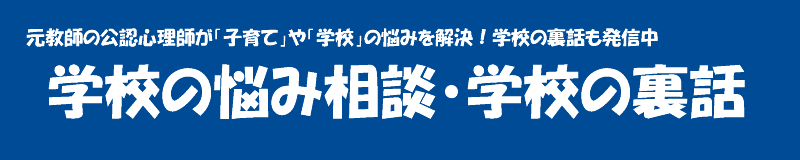



コメント