1.同じ学校に10年いるのはなぜ?
目次
2.離任式は先生達との別れの場
3月は別れの季節です。小学校では6年生、中学校や高校では3年生がそれぞれ旅立っていきます。学校現場では卒業生以外にも先生との別れもあります。
離任式では、「お世話になった先生」と別れることに涙を流す生徒もいるでしょう。できる事なら異動して欲しくない「頼りになる先生」や「優しい先生」「面白い先生」もいるでしょう。
逆に「嫌いな先生」や「やる気のない先生」が異動することを喜ぶ生徒もいるかもしれません。
3.新規採用教員の基本勤務年数は3年
「1つの学校に○何年以上、勤務してはいけない!」
このような法律はありません。しかし、1つの学校に長くいることには「メリット」と「デメリット」があります。
特に若い先生が1つの学校に長くいると、その学校や地域のやり方のみしか知ることができず、教師としての成長が止まってしまうという「デメリット」があります。
そのため、義務教育の先生たちには勤務年数の「目安」があります。その1つが新規採用教員の勤務年数の目安です。
教員の世界では「新採3年」「10年3校」と言われることがあります。これには次のような意味があります。
「新規採用教員の新任学校勤務年数は3年とする。」
「採用後の10年で3校に勤務する。」
4.「10年で3校」は各学校に3年ずつ?
「10年で3校に勤務する」に関しては、下記のような事例も可能となっています。
①3年→3年→3年→(10年目は4校目に異動)
②3年→4年→3年→(10年で3校に勤務)
③3年→6年→4年→(10年目で3校目に勤務)
どのような形であれ、10年の内に3つの学校に勤務すれば良いのです。ただ、コレは目安ですので必ず新規採用教員が3年で異動するわけではありません。
2年で異動する新規採用教員もいれば、最初の学校に4年や5年いる新規採用教員もいるのです。
5.一般教員の基本勤務年数は5年
昭和の時代には1つの学校に「10年」も居続ける先生がそれなりにいました。ただ、平成や令和では1つの学校に長くいる先生はほとんどいません。
現在、一般教員の勤務年数の目安は最長で「5年」と言われています。ただ、部活などで結果を出している先生が、1つの学校に5年以上いることは少なくありません。
これは、「保護者の要望」や「議員の命令(?)」などの結果です。
6.教員生活46年で勤務校は3校?
ある学校にバレーボールで全国大会常連の先生がいました。その先生は私が勤務する5年前から、その学校に勤務しています。
3年後。私がその学校を異動することになった時、まだ、その先生は異動となりませんでした。
その先生に異動しない理由を聞くと・・・・。
「保護者から続けて欲しいという希望が多いんだよ!」
「さらには保護者が議員に働きかけている!」
「その議員が教育委員会に命令しているんだ!」
「だから、オレはA中とB中を行ったり来たりしているんだ!」
「オレがこの市を出ることはないと思う!」
「知っている保護者が多くて指導をしやすいからね!」
この先生は教員生活43年(定年後含む)で3つの学校にしか勤務しませんでした。
ちなみに、現在、その先生は市のバレーボール協会会長となっています。
7.校長・教頭の基本勤務年数は2年
校長や教頭などの管理職の基本勤務年数は2年です。
教頭が異動するときは校長が残り、校長が異動するときは教頭が残るというように、必ずどちらかの管理職が学校に残るようになっています。
校長と教頭の2人同時に異動することは滅多にありません。
例外的に長く勤務する校長もいますが、それには様々な理由があります。
実際に私が勤務した学校の校長で「6年」も同じ学校に勤務していた校長がいました。この校長が6年もの長期に渡って異動できなかったのは「裁判が終わっていなかったから」です。
校長がその学校に勤務した年、体育の授業中に事故が起こり、子どもが「下半身麻痺」となってしまいます。
その子どもの保護者が事故に対しての裁判を起こしたため、裁判が終わるまでの間、校長と体育教師は異動ができなくなったのです。
→「先生」や「学校」「子育て」の悩みがある方はこちら!
→「学校の裏話シリーズ」アマゾン電子書籍で販売中!
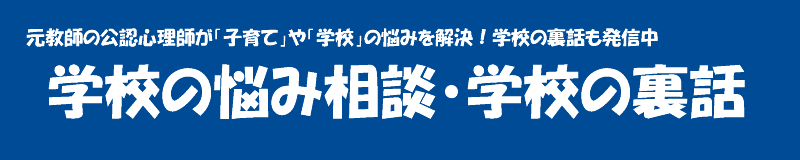



コメント