少しの支援で改善するのに・・・
目次
1.放課後or朝の教員による教室清掃はできる?
次にお願いをしたのは「教室清掃」です。
これは比較的に簡単にできる「学級崩壊改善方法」の1つです。ちなみに、この改善方法は「ブロークン・ウインドウ理論(割れ窓理論)」の考えを学級運営に応用したものです。
ブロークン・ウィンドウ理論(割れ窓理論)とは、アメリカの犯罪学者ケリングが提唱した理論です。
「1枚の窓ガラスが割られている状態を放置していると、それを見た他の人間により、その他の窓ガラスも割られていく。」
「当然、窓を割るという行為が街全体に広がり、軽犯罪→重犯罪が増加し、街が荒廃していく。」
2.学級崩壊クラスの教室は確実にゴミだらけ!
学級崩壊しているクラスは総じて教室にゴミが散らばっています。これは、教師が「清掃活動」を「大切な活動」と考えていなかったことにより起こる状態です。
・元気の良い子(やんちゃな子)が掃除をさぼる。
・担任がサボりに気づかない(気づいても注意をしない)。
・付和雷同組の子たちが掃除をさぼり始める。
・真面目に掃除をしている子たちの「やる気」が下がっていく。
・教室にゴミが増えていく。
※ 付和雷同組の子:教師の様子を見て、良くも悪くも振る舞う子たち
※ この時点で慌てて担任が注意をしても、主犯格の子や付和雷同組の子は言うことを聞かなくなっている。
学級崩壊している時点でクラスの子たちに呼びかけても「掃除」をすることはないでしょう。しかし、教室のゴミをそのままにしていれば更にゴミが増え、モラルや規範意識は低下していくのです。
3.教師がゴミを拾うことで仲間が増えていく!
「教室が汚いままだと、どんどんゴミは増えていきます。」
「ゴミを床に捨てるという小さなルール破りが日常化すると他のルールも簡単に破るようになります。」
「当然、教師の言うことは聞かなくなりますし、問題行動も増えていきます。」
先生たちは私の提案を受け入れてくれない可能性が高いと思いましたが・・・・。
「子どもたちが教室に入る前に先生が教室掃除をするのはどうでしょう?」
「前日の放課後、子どもたちが帰った後で掃除をするのも良いでしょう。」
「毎朝、キレイな教室で子どもたちを迎え入れるのです。」
また、休み時間や授業中にも積極的にゴミを拾ってもらうようにお願いをしました。
「先生の行動を見ている子は必ずいます。」
「これを続けていくと真面目な子たちが先生の味方になってくれます。」
「一緒にゴミを拾ったり、注意をしたりする子も増えてくるんです。」
そして、最後にこのようにお伝えしました。
「手伝ってくれる子のことは帰りの会などで、たくさん褒めてあげて下さい。」
「写真をとって学級通信に載せるのも効果的です。」
「これにより付和雷同組の子も良い状態に戻ってきます。」
4.パワハラを恐れて放課後清掃を命令できない校長
学級崩壊をしているクラスの担任は子どもたちを注意することを恐れています。面倒と思っている担任も少なくありません。
そんな、子どもたちに対して「注意」をしても意味がありません。それどころか担任が精神的に疲れてしまいます。
担任が「ゴミを拾う」や「教室清掃」は、教師の「指導を聞かない子」を注意するという作業ではありません。そのため、担任にとっては、それほど負担がある提案ではないのですが・・・。
「勤務時間外になってしまう可能性があるので、担任に掃除しろと言うのは・・・。」
「授業は『学ぶ場』ですので、担任がゴミを拾うのは・・・。」
「学級通信は担任裁量ですので、配布するように言うことも・・・。」
校長は担任からパワハラで訴えられることを恐れて新しい提案ができないようです。
確かに授業は「学ぶ場」ですが・・・・。
学級崩壊している状態では授業は「学ぶ場」ではなく、「遊び場」になっているのですが・・・。
5.休み時間も教室にいて問題行動を未然防止すればいいけど
次に「休み時間の悪口」や「ベランダからのイタズラ」についての対応を伝えました。
これらの問題行動を防ぐのは簡単なのです。休み時間に教員が教室にいれば良いだけの話なのですが・・・。
「それでは、次の授業の準備ができなくなります!」
「ずっと子どもと一緒では教師が疲れてしまいます。」
「教師にも休憩は必要だと思います。」
「子どもたちの視点で考えても、教師が休み時間に教室にいるのは良くないと思います。」
このように仰る先生方がいます。ただ、これも「学級崩壊あるある」の1つなのです。
「授業の準備は前日までに行うのが普通では?」
「休み時間は教師の休憩時間ではありません。」
「教師のいない休み時間に悪口やイタズラがあるんですよね?」
「悪口を言われている子は先生がいると安心するのではないでしょうか?」
6.休み時間に教室に行くのは不可能と言う学校
休み時間の対応を担任1人でする必要はありません。学年部の先生と交代で対応することも出来るでしょう。
この学校の場合は、校長、教頭、教務(主幹)がこのクラスに関わっています。そうであれば、4人で分担して休み時間の対応をすれば良いのではないでしょうか?そうすれば、1人あたり+10分~20分程度の負担増です。
これだけの負担で「悪口」や「問題行動」が減る可能性があるのです。やらない手はないと思うのですが・・・。
しかし、この対応も校長に却下されたそうです。
「先生たちは授業の準備で忙しいので・・・。」
「ずっと教室にいるのは不可能です。」
「他の先生も自分の仕事を持っているので・・・。」
私は常に教室にいて子どもたちと話していたのですが・・・。
生徒指導主事として「いじめのあった他のクラス」に休み時間ごとに行ったりもしたのですが・・・。
7.子どもを怒るのは教育的に良くない!?
最後に「連携した指導や対応」についてもお伝えさせていただきました。
「生徒指導主任の先生などに、悪役(恐い先生)を演じてもらって下さい!」
「悪いことをしても誰も怒らない状況は良くありません!」
「教師として、大人として、ダメなことはダメと教えてあげて下さい!」
しかし、これに対しても校長はこのように言ったそうです。
「私たちは子どもたちのレジリエンス(回復力)を信じています。」
「怒ったり、管理したり、恐怖政治を行うのは教育ではないと考えています。」
「子どもたち1人ひとりに寄り添い『気づく』ように支援をしています。」
校長のおっしゃる対応で学級崩壊が改善に向かっているのであれば、何も問題はありません。ただ、「自主性」「尊重」「寄り添う」などの理想論にこだわり、現実が見えていないように感じてしまいました。
学校は「問題行動」や「いじめ」を起こしている加害者の人権を大切にする傾向があります。本来は「学級崩壊」や「いじめ」のせいで「辛い思い」をしている被害者に寄り添わなくてはいけないのに・・・。
8.自治的活動が大切!だから、管理教育やゼロトレランスはダメ?
私は、「自治的活動」についての実践論文で「賞」を頂いたこともあります。
(賞金15万円を頂きました。ありがとうございます!)
都道府県の代表となって全国研修会に参加させていただいたり、全国研修会の司会をさせていただいたりもしました。
このような経緯もあり、「自治的活動」については他の先生方より理解しているという自負があります。
そんな私ですが、「管理教育」や「ゼロトレランス」を完全に否定する立場に立っている訳ではありません。
※ 管理教育:校則やルールをなどで子どもを管理する教育。
※ ゼロトレランス:寛容0(ゼロ)。ルールを破った場合は問答無用で罰する。
先生方には「自治的活動」の素晴らしさを理解し、それを実現させるために努力をしていただきたいと思っております。
ただ、教師の力が及ばず「学級崩壊」が起こっているのであれば、「管理教育」や「ゼロトレランス」を取り入れたほうが良いとも思っています。
「自治的活動を謳って学級崩壊する位なら、管理教育やゼロトレランスで学級崩壊を防ぐ方が良い。」
理想の対応ばかりではなく、現実に即した対応が必要と考えているのです。
9.ゼロトレランスでいじめ被害者は安心!
学級崩壊のクラスには、必ずと言っていいほど「いじめ」や「不登校」が起きてしまいます。そこで、「管理教育」や「ゼロトレランス」を行うと、学級崩壊の中心人物(加害者)たちは「窮屈」な思いをすることでしょう。
反対に「いじめ」の被害者や「不登校」の子たちは「安心感」をもつようになります。なぜなら、「いじめ」の被害者や「不登校」の子たちは、学校の「ルールを守る」子であり、仲間の「悪口を言わない」子だからです。
当然、「いじめ」の被害者や「不登校」の子たちが、「管理教育」や「ゼロトレランス」をしている教師から怒られることはありません。なぜなら、「ルールを守り」「悪口を言わず」「いじめ」をしないからです。
もちろん、「授業中に出歩く」「おしゃべりをする」「友だちの悪口を言う」「問題行動を起こす」子たちは、教師に怒られる回数が増えるでしょう。
これにより、クラスの真面目な子たちは教師に対して「安心」や「信頼」を持つようになるのです。
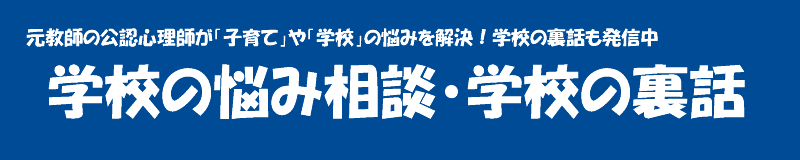



コメント