話し合いで問題を解決しようとするが・・・
目次
1.学級崩壊の対応はたくさんあるけど・・・・
私は相談を受けたお母さんに「授業の感想」を全て伝えました。すると、お母さんはこのように聞いてきます。
「どうしたら学級崩壊を改善できますか?」
「改善方法を教えて下さい!」
「私から校長に伝えます!」
しかし、私にはこのような危惧がありました。
『学級崩壊を解決する方法はあるけど・・・・・。』
『校長や担任が本気でやれば解決するけど・・・・。』
『勤務時間内ではできないとか言われそうだし・・・・。』
お母さんに、このような心配があることを伝えた上で、私は学級崩壊の対応をお伝えしました。
2.学級崩壊あるある:話し合いで問題を解決しよう
「クラスの問題は子どもたち同士で話し合って解決させます。」
「教員が命令したり、注意をしたりして、問題を解決しても意味がありません。」
「子どもたちが自主的に問題に向き合い、自分たちで解決することが大切です。」
「私はクラスや友だち同士で問題があったときは、子どもたちに話し合いをさせます。」
「自分たちで問題を解決することは生きる力になると思っています。」
このように仰る先生は少なくありません。確かに仰ることは間違っていません。子どもたちが自分たちで問題を提起し、その対応を全員で考え、それを解決することが出来れば、これほど素晴らしいことはありません。
しかし、自分たちで問題を提起し、自分たちで解決できるクラスは、どのくらいあるのでしょうか?
私は教員生活25年の間、常に学級担任をしてきました。また、学級運営や人間関係の構築研究に力をいれてきました。その結果、「自分たちで問題を提起し、自分たちで解決できる」クラスを作ってきた自負があります。
ただ、「自分たちで問題を提起し、自分たちで解決できる」クラスを作ることができたのは40代に入ってからです。それ以前は、もちろん良いクラスだった自負はありますが、全てを自分たち解決できるクラスではあったかと聞かれると・・・。
3.学級活動での話し合い禁止!
学級崩壊を解決するため、私が最初に伝えた対応は「学級活動での話し合い」をやめることです。
なぜ「学級活動での話し合い」の中止を最初に伝えたのかというと、授業参観の時に次のような掲示(言葉)を多く目にしたからです。
「学級の問題点を解決するための5箇条!」
「みんなで決めたルール!」
「学活で話し合ったことを守ろう!」
「トラブルが起きたときは話し合おう!」など
背面黒板、教室後方掲示場所、教室横掲示場所にこれらの言葉が貼られていました。前面黒板を見ると「みんなで決めたルール」と書かれた掲示物が貼られています。
・先生や友だちの話はしっかりと聞こう!
・授業中のおしゃべりをやめよう!
・授業中に出歩くのをやめよう!
・時間を守ろう!
・悪口は言わないようにしよう!
※ なぜ、「悪口禁止」と書かないのでしょうか?
そして、最後に次のような言葉が書かれていました。
「みんなで話し合って決めたことは守ろう!」
しかし、「みんなで決めたルール」が守られている気配はありません。
4.目標を掲げるのは良いことだけど・・・
目標を掲げ、それを達成(守る)ことができれば子どもたちの「自己効力感」や「自己肯定感」は高まるでしょう。しかし、目標を掲げても、それを達成(守る)ことができなければ、当然、「自己効力感」や「自己肯定感」は上がりません。
子どもたちの「自己効力感」や「自己肯定感」が変わらないのであれば、まだ良いのですが・・・・。
「守らなくても何も言われない!」
「誰にも怒られない!」
「みんなで決めたことは守らなくていいんだ!」
このように、子どもたちが誤学習してしまうと・・・・・。
子どもたちの「自己効力感」や「自己肯定感」を高める以前の問題として「学級崩壊」が起きてしまうのです。
5.自主性や自治を育てるには基礎が大切!
担任が「クラスの問題を話し合いで解決することが大切」と思っているのは、「学級崩壊あるある」の1つです。
「私は子どもたちの自主性を尊重しているんです。」
「クラスの問題を自分たちで考え、自分たちで解決することが大切だ!」
「教員がルールを押しつけるのは良くない!」
「自分たちでルールを決めることで、子どもたちはルールを守るようになる!」
「子どもの成長には自治的活動が必要なんです!」
確かに仰ることは「理想の対応」だと思います。しかし、教師が「理想の対応」を行ったからと言って、子どもたちが必ず「理想の行動」を取るわけではありません。
更に言えば、子どもたちが「自治的活動を行えるようにするには、「話し合いの基礎」や「人権感覚」、「自己効力感」「他者理解」「モラル」などのスキルや知識の基礎が必要不可欠です。
教師がこれらの指導や支援をせず、ただ「自主性が大切!」「自治をさせたい!」と言っても、子どもたちが上手にできるわけがないのです。
6.教師が「強い指導」をしてはいけないの?
次の①~④の「教師の対応」と「子どもたちの活動結果」の中で、あなたが「良いクラス」と思えるのはどれですか?
可能であれば順位をつけて下さい。
①教師が「理想の対応」を行ったことで、子どもたちが「自治的活動」を行えた。
②教師が「理想の対応」を行ったが、クラスは「学級崩壊」してしまった。
③教師が「強い指導」を行ったことで、子どもたちが「自治的活動」を始めた。
④教師が「強い指導」を行ったことで、クラスは「学級崩壊」してしまった。
当然ですが、教師が①の対応を行い、子どもたちが①の結果を出してくれることが最も望ましいでしょう。
それでは、2番目に良いクラスと思われるのは②~④のどれでしょう?
②のように教師が「理想の対応」を行うことでしょうか?
それとも、③のように教師が「理想の対応」ではなくても、子どもたちが「自治的活動」を始めることでしょうか?
私は「理想主義者」でもありますが、「現実主義者」でもあります。そんな私が2番目に良いクラスと思うのは③のクラスです。
なぜなら、③のクラスには「辛い思い」をする子がいないからです。
確かに③では、「自己効力感」や「自己肯定感」はそれほど上がらないかもしれません。それでも、「辛い思い」をする子がいない状態にはなっています。
1人ひとりの能力を高めることは大切ですが、全ての子が安全に生活できる環境を提供することの方が大切ではありませんか?
もしかしたら、子どもたちの「成績」や「能力」「スキル」は成長しないかもしれません。それでも、教室が誰1人「辛い思い」をしない空間である方が良くないですか?
いじめや無視、悪口などがなく、みんなが笑顔で過ごせる教室。1人ひとりの居場所がある教室が良いと思いませんか?
7.学級崩壊しても自分のやり方を変えない教師
私は①~④に次のような順位をつけます。
「①→③→④→②」
3番目に良い状態を④とし、最も悪い状態を②とした理由は「その後の教員の対応」を考えたからです。
「私は子どもたちの自主性を尊重しているんです。」
「クラスの問題を自分たちで考え、自分たちで解決することが大切だ!」
「教員がルールを押しつけるのは良くない!」
「自分たちでルールを決めることで、子どもたちはルールを守るようになる!」
「子どもの成長には自治的活動が必要なんです!」など
このように考えている教員は、クラスが学級崩壊したときに次のように考える傾向があります。
「前の学校では上手くいった!」
「だから、私の対応は間違っていない!」
「悪いのはクラスの子どもたちだ!」
「親がちゃんと子育てをしていないからだ!」
「私は何も悪くない!」など
このように考える教員は、自分の対応を変えようとしません。当然、クラスの状態は更に悪くなってしまうのです。
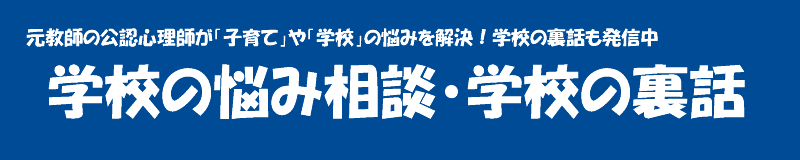



コメント