1.子どものため?教師が楽(らく)するため?
目次
2.4月の登校日で新クラス発表だったのに・・・
春休みが終わり学校に登校すると昇降口には人だかりができています。
人だかりの先には「新しいクラス」の名簿が張り出されていました。
「やった~!」
「Aくんと同じクラスだ!」
「Bちゃん一緒だね~!」
「CさんもDさんもいる!」
喜びの声と同時に悲しい思いをしている人もいるでしょう。
『Eさんと別のクラスになっちゃった・・・。』
『同じクラスにFくんがいる・・・。』
『えっ?』
『同じ部活の人が1人もいない!』
『誰のグループに入ればいいんだろう・・・。』
3.3月にクラスを発表するのは作業効率のため!
ただ、最近は3月の終わりの離任式にクラスを発表する学校が増えています。これには理由があります。
・離任式の日に新しいクラスに机を移動させることができる。
・春休み中に新入生のクラス準備ができる。
・(先生たちが)春休み中に新年度の準備ができる。
・保護者が名札やノートなどに記名することができる。など
ある学校で生徒指導主事をしていたとき、「離任式に新クラスを発表する」理由を校長に聞いてみました。
「不登校や不登校傾向の子に早くクラスの仲間を伝えてあげたい!」
「新クラスを知ることができれば、4月から安心して登校できるようになる!」
確かに新クラスのメンバーを早く知ることで安心できる子もいるでしょう。ただ、逆に不安が大きくなり登校できなくなる子どもがいるのも現実です。
この校長は「不登校の子どものため」と言っていましたが、私の経験では「学校の作業効率を優先するため」という方がしっくりきます。
4.少しでも良いクラス編成をしたい!
私は「新クラスは4月に発表する方が良い」と考えています。なぜなら、春休みの部活動などで「子どもたちの人間関係」の最終チェックをしたいと思っているからです。
「私に見えていた人間関係は正しいのか?」
「A先生が言っていた人間関係は本当か?」
「BとCは一緒でいいのか?」
「Dが活きるためにはEと同じクラスの方が良いのでは?」
そして、次のようにも思っていました。
「新学期の人間関係が少しでも円滑になるようにギリギリまで確認をしたい。」
「全ての子どもが楽しく学校生活を送れるようにギリギリまで人間関係を考えたい。」
「我慢をしすぎる子がいなくなるように、ギリギリまで相性を調べたい。」
5.優しい子の善意を利用する教師
ある担任がクラスの子どもについて次のように言っていました。
「AはBと同じクラスにしてほしい!」
「なぜならAはBの面倒を見てくれるから!(お世話係)」
「Aさんに任せておけばBさんが1人になることはない!」
この担任はAさんの気持ちを全く考えず、発達障害のグレーゾーンのBさんの事だけを考えいました。Aさんの優しい気持ちを利用してBさんのお世話をさせようとしていたのです。
※ 担任の先生に悪気はなかったようですが、それも問題だと思います。
6.人間関係の表面しか見ていない教師
他の担任は次のように言っていました。
「CはDと同じ部活で2人ともレギュラーだ!」
「2人を一緒にすれば部活の良い関係がクラスでも発揮される!」
「他の子にも良い友人関係を広げてくれる!」
しかし、部活の様子をみていると、どうも担任の言っていることが間違っているような気がします。私は顧問の先生(他学年)にCとDの関係を聞きました。
「CとDは良く言えばライバルです。」
「ただ、2人とも我が強いので対立してしまうときがあります。」
「実際、2学期の部活ではどちらが部長になるかで揉めました。」
「試合に勝つためには協力をしますが、練習中の雰囲気は良くないんです。」
若い顧問の先生は私に次のように言いました。
「可能であれば別のクラスにしてもらった方が・・・。」
「同じクラスでは対抗心が出てしまうと思います。」
「それが部活にも影響しそうで怖いです。」
私は「AとB」「CとD」について主任や担任に相談をしました。最終的には、春休みに小会議を行い「AとB」「CとD」は別のクラスにすることにしたのです。
7.新担任との相性は大丈夫?
新担任についてもギリギリまで考えて決めたいと思っていました。特に赴任したばかりの先生に担任をお願いするときは慎重に相性を見極めなければなりません。
過去に別の学校で一緒に働いた事がある先生であれば、その先生の性格やキャラが分かっています。当然、その先生に合った「クラス」や「子ども」をマッチングすることが出来ます。
しかし、初めて一緒に働く先生の性格やキャラは分かりません。そのため、たった数日となりますが、その先生の性格やキャラを見極め、少しでも合った「クラス」や「子ども」をマッチングするように意識をしていました。
もちろん、ギリギリまで考えたからと言って、全てが完璧になるわけではありません。それでも、少しでも多く考えることで「子どもたちが楽しい」と思えるクラスが出来る確率を上げたかったのです。
8.子どもたちの為だったんじゃなかったの?
私は生徒指導主事として職員会議において上記の考えを伝えてきました。しかし、「少しでも」という私の考えに賛同する先生は一握りです。(25年の教員生活で数人です。)
私が職員会議で提案をすると・・・。
「そんなに細かく考えても変わらないよ!」
「ギリギリに変更したら名簿を作り直さなきゃならないでしょ!」
(名簿の作り直しなど、たかだか10分程度で終わるのですが・・・。)
「誰が担任をしても一緒だよ!」
「不登校や問題行動は親や本人のせいなんだから!」
「自分の思い通りじゃなくても我慢させなきゃ!」
また、次のように言われたこともあります。
「事務作業が遅れて先生たちの仕事が進まない!」
「4月に入ってからやることが増えてしまう!」
「教員の多忙につながってしまう!」
「完璧なんてムリなんだから割り切らなきゃ!」
離任式で発表するのは「子どもたちのため」と言っていたのに・・・。
9.「仕事の効率」or「子どもの充実」
仕事が効率的に進むように制度や慣習を見直すことはとても大切です。ただ、クラス編成と担任決定には「子どもの1年」がかかっています。
先生たちは「教育のプロ」なのですから、どのようなクラスも「良いクラス」にしなければならないのですが・・・。
そこまで指導力(支援力)のある先生は少ないのが現状です。(指導力は無くても気持ちがあれば良いのですが・・・。)
結果的に先生たちは「仕事の効率」と「子どもの1年」を比べた場合、「仕事の効率」を優先してしまいます。
学校は子どもたちの成長を促す場です。そのためには「安心」「安全」「居場所」が必須なのですが・・・。
「毎日、楽しく過ごせるクラスにしよう!」
「子どもの得意や良さが活きるクラスにしよう!」
「学校に行くのが楽しいと思えるクラスにしよう!」
「1人ひとりの居場所があるクラスにしよう!」など
これらの目標を実現するためには「何が必要なのか?」を常に考えていただきたいのですが・・・。
これが「教育のプロ」である先生の仕事だと思うのですが・・・。
10.4月は1年で最重要月間!
4月は1年で最も大切な時期です。子どもたちも心機一転ガンバろうと考えています。だからこそ、教師も最も力を入れなければならない時期なのです。
実際、私は中学1年生の担任をする4月を最重要と考えて支援や指導を行ってきました。中学1年の4月に「正しい対応」や「正しい支援」を行うと、子どもたちの「自治的活動」が活性化するからです。
また、1~3学期で考えると、やはり「1学期」が最も重要な時期となります。
11.事前支援による未然防止の観点を!
これは、事前支援による「未然防止」の考えからきています。
普通の先生たちは子どもたちが「問題を起こした」後に対応や指導を行います。しかし、「未然防止」では次のように考えます。
「子どもたちが問題を起こさないように事前支援に力を入れよう!」
もし、あなたが「子どもの問題行動」に10時間を費やしたのであれば、同じ10時間を「未然防止」に使ってみてはどうでしょう?
同じ10時間でも、子どもたちを「怒る」指導より、子どもたちを「褒める」支援の方が良いと思いませんか?
→「先生」や「学校」「子育て」の悩みがある方はこちら!
→「学校の裏話シリーズ」アマゾン電子書籍で販売中!
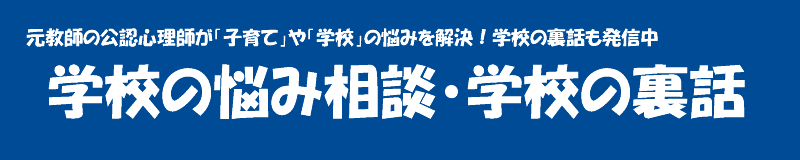
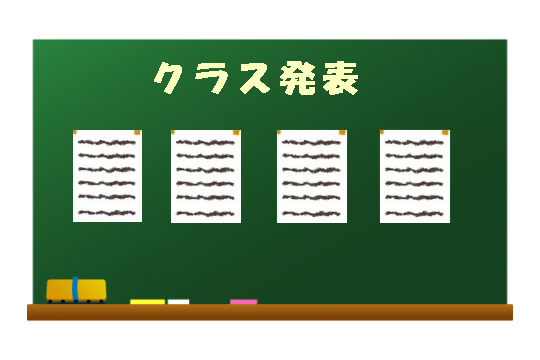


コメント