ヤンキー系の子の「お世話係」として7年間同じクラスに!?
目次
1.イライラしているときは「お世話係のモモちゃん」にお任せ!?
私は「お世話係」と思われる子に「お世話をしなくていいよ!」と言ったことが何度もあります。これに対して、全ての子どもが私にお礼を言ってきました。
クラスの子どもの支援は教師の仕事なのですからお礼を言われる筋合いはないのですが・・・。
ヤンキー系のホノと言う子がいました。小学校では「ホノ」=「モモちゃん」と決まっていたそうです。1学年2クラスの小規模校だったためか、ホノとモモちゃんは7年間同じクラスでした。
ホノが問題を起こしイライラしているときはモモちゃんの出番です。モモちゃんがホノに声をかけ、ホノを落ちつかせてくれるようです。
私はモモちゃんに「ホノのお世話をしなくていいよ!」と声をかけました。しかし、優しくて真面目なモモちゃんは「大丈夫です!」と言ってお世話を続けます。
2人が中学2年生になるとき、私はホノとモモちゃんを同じクラスにするか悩みました。その理由は次のように思ったからです。
「もしかしたら、モモちゃんにとってホノは必要な存在なのかもしれない!」
ただ、ホノやモモちゃんの日々の様子を観察したり、親御さんの言葉を聞いたりして、最終的にはホノとモモちゃんを別のクラスにしたのです。
2.中2では別のクラス!お世話係から解放されたモモちゃんは?
新中学2年生の初日。新クラスの名簿を見たモモちゃんは、スグに私の所にきました。
「先生、ありがとうございます。」
ホノと別のクラスになったモモちゃんは、様々な場面で活躍するようになりました。テストでは常にトップ3に入るようになりましたし、部活では個人戦で準優勝を勝ち取りました。学級委員や生徒会にもチャレンジしていました。
この様子を見た私は、中学3年生でもホノとモモちゃんを別のクラスにしました。ちなみにホノは3年間、私のクラスです!(笑)
卒業した教え子からの突然の電話の内容は?進学の相談?進路の相談?恋愛の相談?不倫の相談?悲しい相談?ホノからきた連絡は○○の相談だった・・・。
卒業式の後、モモちゃんのお母さんが私の所にきて手紙を下さいました。
「先生のおかげでモモは元気を取り戻しました。」
「中学2年生でホノちゃんと別のクラスになってからは、明らかに笑顔が増えました。」
「モモはホノちゃんの悪口を言ったことがありません。」
「それでも、ホノちゃんのお世話係は大きな負担になっていたと思います。」
「先生がモモの気持ちに気づいて下さって本当に良かったです。」
「ホノちゃんと別のクラスになったことで、モモは救われたと思います。」
「ホノちゃんには申し訳ありませんが、モモの親としては別のクラスにしていただいた事は感謝しかありません。」
「本当に本当にありがとうございました。」
3.「お世話係」は必要?頼まれた子どもの気持ちを考えて!
不登校や発達障害の子の数は増える一方です。そんな中、先生たちは「多忙」を理由に「お世話係」をつくってしまいます。
本来は不登校の子どもや発達障害の子どもの支援は教員の仕事なのに・・・。
お世話係になる子どもは「真面目」「優しい」「我慢強い」子がほとんどです。そんな子どもたちが自分から友だちを「フォロー(お世話?)」するのは良い事です。仲間がお互いに助け合ったり、苦手な部分をフォローし合ったりすることは社会に出ても必要なことだからです。
しかし、「真面目」「優しい」「我慢強い」子どもたちの善意を利用して、勝手に「お世話係」を任命するのは良いことなのでしょうか?
もちろん、子どもたちが手伝ってくれれば教師は楽(らく)になるでしょう。ただ、「手伝い」を「係」として強制するのはおかしいのではないでしょうか?
4.職員会議でお世話係廃止を訴えるも・・・
私は生徒指導主事として「お世話係の子ども」について職員会議で話をしたことがあります。
「気になる子や手のかかる子の個別の支援は教師の仕事です!」
「特定の子に『お世話係』を頼むのはおかしいのではないでしょうか?」
「子どもの善意を利用して『お世話係』を作るのはやめましょう。」
「友達の『お世話』を頼まれた子の気持ちも考えてあげて下さい!」
私の発言に対して、このような意見が返ってきました。
「発達障害を持っている子をクラスが受け入れるのは当然だと思います!」
「仲間の特性を理解し、受け入れ、フォローするのは当たり前ではないですか?」
「クラスの仲間で助け合うことが間違っているのですか?」
「西川先生の考えは理想論だと思います。現実をみて下さい!」
「先生たちは忙しいので1人ひとりに細かい対応はできないと思います。」
「お世話係に選ばれて喜ぶ子もいるのではないですか?」
「ムリにお世話係を無くす必要はないでしょう。」など
5.お世話するのは「当たり前」じゃない!
もちろん、私の意見に賛成して職員会議終了後に声をかけてくれた先生もいます。個別の支援や対応の具体的なアドバイスを求めてきた先生もいます。
しかし、ほとんどの先生が「多忙」を理由に「お世話係」を肯定していました。
子どもたちが、善意で自ら仲間のお世話をすることを否定しているわけではありません。前述したとおり「仲間同士で助け合う」ことは大切であると思っているからです。私が問題としているのは、教師が勝手に「お世話係」を任命してしまうことなのです。
クラスの子どもの支援は教師の仕事です。子どもたちが善意で手伝ってくれたのであれば、教師は「ありがとう!」とお礼を言わなければなりません。なぜなら、教師の仕事を手伝ってくれたからです。
お礼を言われた子どもは、また、手伝ってくれるかもしれません。当然ですが、そのときも「ありがとう」とお礼を言うのが普通ではないでしょうか?
クラス替えの時に「お世話係」を作る先生も、最初は「お願い」をしていなかったのかもしれません。もしかしたら、気になる子に対して「どのように支援をすればいいのか?」と悩んでいたのかもしれません。
そんな先生を見たクラスの子どもたちは、善意から先生を手伝ってくれたのでしょう。先生も最初はお礼を言っていたのでしょう。しかし、「手伝ってくれる」状態が続いたことで、先生はそれを「当たり前」と思ってしまったのかもしれません。
6.3年間かけて説得!進路を変えさえた!
「先生!私、中学校の先生になりたい!」
「子どもの気持ちが分かる先生になるんだ!」
モモちゃんとユメちゃんは、このように言っていました。「西川先生みたいな先生になりたい!」モモちゃんとユメちゃん以外にも、このように言ってくれた子が何人もいます。この子たちは総じて成績の良い子たちです。
この子たちは、私が友達関係をよくするため、意図的に言った言葉や、わざとおこなった行動に気づいていました。そして、それを指摘してきました。
「先生!あのとき怒ったのわざとでしょ!」
「AちゃんとBちゃんが仲直りしやすくするためでしょ!」
周りの事を冷静にみることができ、さらには、優しく、真面目で、ガンバリ屋の子どもたちです。そんな子たちが「先生になりたい!」と言ってくれるのは教師冥利につきると言うものです。
そんなモモちゃんやユメちゃん、他の子たちに私は自分の気持ちをハッキリ伝えました。
「いいか!」
「先生にだけは絶対になるな!」
「君にはもっと明るい未来が待っている!」
「絶対に先生はダメだぞ!」
「分かったなっ!!!!!」
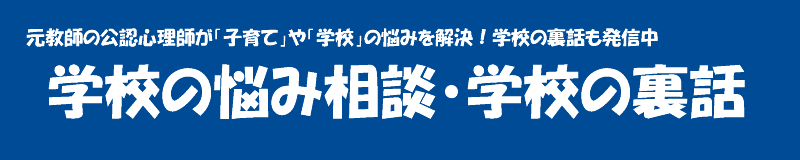



コメント