荒れている他校にキレた審判を最も恐れたのは・・・
目次
1.学年の先生は指導しなかったけど
修学旅行で問題行動を起こした男子のAとBは、私が顧問をしている部活に在籍していました。
そんな子供たちに対して私は注意を促します。
「どんな理由があってもルールは守りなさい!」
『○○だから許される!』
『□□だから仕方ない!』
「先生はそれを許さないし仕方ないとは思わない!」
「やるべき事をシッカリとやりなさい!」
私の本気を感じたAとBの表情が少し締まったように見えました。
元々、この学校の3年生は悪い子供達ではありません。
3年部の先生達が「間違った支援」や「指導」をしているせいで、子供たちが「調子に乗って」いるダケなのです。
2.大会で活躍できるように練習試合を!
「大会で勝ち上がれるように練習に集中しよう!」
「練習試合をたくさんして試合経験を積もう!」
「県大会出場(地区大会で優勝or準優勝)を目指してガンバろう!」
私は可能な限り「朝練」や「放課後練習」を行い、子供たちの「やる気」に応えます。
もちろん、試合経験を積ませるため多くの「練習試合」も計画しました。
他の学校と「練習試合」をするたびに、子供たちの「態度」や「姿勢」「やる気」が高まっていくのが分かります。
後に3年生から話を聞いたところ・・・。
「練習試合をしたのは始めてだった!」
「1回だけじゃなく何回も練習試合を組んでくれた!」
「自分たちの実力やランクが分かった!」
「少しずつ勝てるようになって楽しくなった!」
どうやら、前顧問は「練習試合」など手間のかかる事はしていなかったようです。
3.夏の大会で3位に!さらに嬉しい言葉が!
私は中体連の組み合わせ抽選会で「良い番号」しか引いたことがありません。
本来はベスト8の実力の子供たちを「くじ運」で準優勝に導いたり、本来は1~2回戦負けのチームを4回戦まで進出させたりしてきました。
この時の中体連でも、私は「くじ運」の強さを発揮します。
結果を先にお伝えすると、実力的には「ベスト8」だった所を組み合わせにより「3位」となれたのです。
もちろん、子供達が練習の成果を発揮できた結果である事は間違いありません。
残念ながら「県大会出場」を逃してしまった子供達ですが、閉会式では指導校長から「試合態度」について嬉しい言葉をいただくこととなります。
4.1回戦はラフファイトと暴言のA中学校
話は中体連の1回戦に戻ります。
1回戦の相手は「荒れている」と評判のA市の北中学校です。
学校が「荒れている」だけあって「ラフファイト」や「暴言」が多い学校です。
対する西中の3年生は、学校内では「調子に乗っている」のですが、外では大きな態度を出せません。
『もしかして、北中学校にビビって力を出し切れない?』
『北中学校の子供が怖くなって戦えない?』
『実力的に負けることはないんだけど・・・。』
『もし、負けるとしたら力を出し切れないパターンだな!』
私は子供たちに声をかけます。
「平常心で試合に臨もう!」
「練習の時のように落ち着いていこう!」
「相手の事は考えず自分のベストを尽くそう!」
「いつもの状態なら負けることはないから大丈夫!」
しかし、子供たちの表情を見ると・・・・。
5.相手の暴言にビビってしまう子供たち
試合が開始してスグに北中学校が「ラフプレイ」を仕掛けてきます。
「お~い!」
「どうしたんだよ~。」
「もっと、来いや~。」
「どんどん、かかって来いや~!」
北中学校の選手が挑発してきます。
これに対して、私の3年生達は・・・。
完全に北中学校の子供達の「ラフプレイ」と「暴言」にビビってしまっています。
しかし、北中学校の「ラフプレイ」や「暴言」に対して、審判の先生が強い指導をしてくれます。
「おいっ、北中!」
「その言葉使いは何だ!」
「ラフプレイも許さん!」
「次にやったときはスグに退場にするからな!」
審判の先生は、地域でも評判の「昔ながらの体育」の先生だったのです。
6.反抗的な態度を審判に強く指導される北中
審判に指導を受けた北中学校の子供たちは「ラフプレイ」や「挑発」をしなくなりました。
しかし、試合中の態度は良いモノではありません。
得点した相手選手を睨んだり、ボールを投げつけたりします。
そんな様子を見ていた審判は、北中学校を指導するタイミングを見計らっていたようです。
そんな中、北中学校の子供がファールをしました。
ただ、その子供は判定に納得がいかなかったようで審判を睨んでいます。
そして、審判に渡すべきボールをあろうことか、審判と逆方向に蹴ってしまったのです。
「何だその態度は!」
「ふざけるな~!」
「顧問もコッチに来い!」
7.怒る審判を恐怖に感じたのは・・・
審判の指導に対して、最も驚き、最も恐怖を感じたのは北中学校の生徒ではありません。
もちろん、北中学校の顧問の先生でもありません。
審判の指導に最も驚き、最も恐怖したのは西中学校の3年生だったのです。
もちろん、この試合において西中学校の3年生は何も悪いことはしていません。
それどころか、北中学校の雰囲気に飲まれないようにガンバっていたのです。
それでも、普段の学校で「3年部の先生達」から怒られた事がない3年生にとって、大きな声で怒鳴る審判は「恐怖の存在」となってしまったようです。
幸いにも、審判を「恐怖」に感じた事はプレーに影響しませんでした。
ただ、相手チームや自分のチームがファールをすると・・・。
審判を恐れている西中学校の3年生は、ダッシュでボールを取りに行き、ダッシュで審判に渡します。
さらには、ボールを審判に渡すとき、頭を下げて大きな声で次のように言うようになっていました。
「ボールを持ってきました!」
「ヨロシクお願いします!」
8.閉会式で拍手喝采を受ける子供たち
無事に1回戦を突破した後も、3年生は「素早いボール拾い」と「丁寧な声かけ」を続けます。
完全に「審判」=「怖い」と勘違いしてしまったようです。
私の「くじ運」もあり、子供たちは順当に勝ち上がっていきました。
ただ、残念ながら準決勝で負けてしまい、県大会出場の目標は達成できませんでした。
※ もしかしたら、ボールを拾いに行くときの無駄なダッシュが原因かもしれません。(笑)
しかし、自分たちのファールの時だけでなく、相手チームのファールの時も「ダッシュでボールを拾い」に行き、審判に「丁寧な声かけ」を行った行動は、顧問の先生達から評価されます。
その結果、準々決勝、準決勝と試合を見て下さった「指導校長」が閉会式でお褒めの言葉を下さったのです。
「C中学校の生徒の試合へ臨む態度は素晴らしかった!」
「相手チームへのリスペクトも感じた!」
「審判への声かけは本当に丁寧だった!」
「県大会出場こそ逃したが、試合に対する姿勢はダントツの優勝だ!」
「これは私だけの考えではない!」
「他の学校の顧問や保護者達も同じ考えだ!」
「みなさん!」
「西中学校の生徒に拍手をお願いします!」
会場中に西中学校の3年生をたたえる拍手が響き渡りました。(笑)
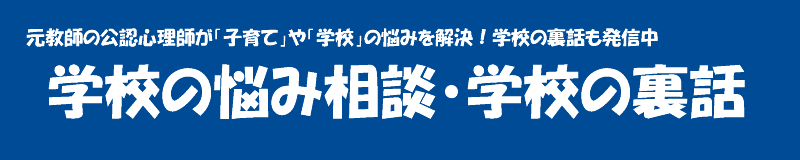



コメント